
北海道・釧路で、傷を負った野生猛禽類の治療や調査研究を行う「猛禽類医学研究所」が今週のチャリティー先。
自動車事故や列車事故、風力発電のプロペラとの接触、感電事故など、収容される個体の原因のほとんどに、人間の活動が影響していると指摘するのは、代表で獣医師の齊藤慶輔(さいとう・けいすけ)先生。
「怪我しているところを偶然発見されて、我々のところに運ばれ、治療を経て野生復帰するというのは本当にごくわずかで、氷山の一角。
人間の責任として、傷を負った個体に関しては、治療して野生に返すし、人間が関わっていることが原因であるならば、根本的に対策し、なくしていく必要がある」と話し、野生生物との共生を目指し、「環境治療」にも力を入れています。
活動について、お話を聞きました。

お話をお伺いした齊藤先生

猛禽類医学研究所
環境省の委託を受け、傷病野鳥の治療やリハビリを行っています。
治療だけでなく、傷病または死体収容された個体の原因を探ることや現場で調査をすることで、環境で起きている異変や私たち人間が与えてしまっている影響などの問題を紐解き、具体的な対策の提案と実行を試みています。
INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO
RELEASE DATE:2025/08/11

交通事故で猛禽類医学研究所に収容されたオオワシの放鳥シーン
──今日はよろしくお願いします。最初に、団体のご活動について教えてください。
齊藤:
絶滅の危機に瀕した野生の猛禽類を対象に、保全活動全般を行っています。
シマフクロウやオジロワシ、オオワシといった猛禽類は、生態系ピラミッドの頂点におり、生態系の中で重要な役割を果たしています。「アンブレラ種」と言って、その地域の猛禽類を守ることは、その傘下にあるさまざまな動物や植物、生態系を守ることにつながります。
もうひとつ、猛禽類は「キーストーン種」でもあります。
キーストーン種とは、生態系全体のバランスを保つ上で、非常に重要な役割を果たす種のことで、その種がいなくなると生態系に大きな影響を与えてしまいます。
猛禽類に焦点を当てながら、自然環境が健全な姿で、末長く存在し続けられる世界を目指して活動しています。

救護の際に使用しているドクターカー。車内には酸素室(新生児用のインキュベーター)や、処置台などを設置しており、救命率をあげるための設備が整っている
齊藤:
さまざまな活動の一つとして、猛禽類医学研究所では、活動拠点である環境省釧路湿原野生生物保護センターにて、収容された傷病個体の収容・治療・リハビリテーション・野生復帰を行っています。
収容した猛禽類が生きていようと死んでいようと、なぜこんな姿になってしまったのか野生動物法医学の知識を駆使してつぶさに調査し、その原因を究明してきました。
私が活動を初めて今年で31年になりますが、治療した傷病個体、あるいは死体を検分すると、その原因に、ほとんどの場合において人間の活動が関わっていることがわかりました。

環境省が毎年実施している標識調査で行った健康診断にて、身体の発達に左右差があり、神経性の発作を起こすシマフクロウのヒナが見つかった。野生で生きてくことは厳しいと判断され、終生飼育個体となった。「ちび」と名付けられ、シマフクロウ親善大使として教育普及や活動啓発の場で活躍した
齊藤:
怪我しているところを偶然発見されて、我々のところに運ばれ、治療をした結果、野生復帰するというのは本当にごくわずかで、氷山の一角でしかありません。
人間の責任として、傷を負った個体に関しては、治療して野生に返すということをやっていますし、人間が関わっていることが原因であるものに関しては、根本的に対策して、排除していく必要があります。これ以上増やさないために「環境治療」に力を入れています。

サハリン北東部で12年間行ったオオワシの繁殖状況調査。衛星送信機を用いた追跡調査により、サハリンで繁殖するオオワシの多くが北海道で越冬することが明らかになった。繁殖地においては大規模な石油天然ガス開発が進められており、石油流出などの事故が起こった際にオオワシの繁殖地に壊滅的な影響がもたらされるとともに、油汚染のリスクが北海道にまで及ぶことが懸念される

交通事故に遭い、道路脇で動けない様子のシマフクロウ
──猛禽類は、どんな理由で収容されるのでしょうか。
また、どのような対策をしておられるのですか。
齊藤:
交通事故(自動車事故、列車事故)は多いです。
ワシやシマフクロウが、車に轢かれた小動物や道路を渡っているカエルなどを餌として狙って路上に降りた時に自動車と接触してしまうことが少なくありません。
また、釧路市を含む道東地域は川(シマフクロウの移動ルート)と道路(人間の移動ルート)の交差点となる橋がたくさんあり、ワシやシマフクロウが橋の上を低く飛んで通過する際、車と衝突することもあります。
交通事故を未然に防ぐ対策として、路面に溝を刻んでガタガタにして、タイヤの音と振動で車の接近を認識させる「グルービング」の導入に取り組んでいます。

道路に施されたグルーピング。車が上を通ると、音と振動が発生し、路上のシマフクロウに車の接近を知らせて交通事故を予防する
齊藤:
これは猛禽類にとってだけ良いものではなく、冬の道路凍結によるスリップ事故防止、人間の交通事故防止にも役立つもので、各道の管理者(国道であれば国土交通省、市道であれば市役所など)とは、そのようなかたちで合意を得て、各地で採用していただいています。
橋の上での接触事故に関しては、欄干の上をそのまま飛ぶと、猛禽類が飛ぶ高さと車の高さが同じぐらいで車と接触してしまうので、「ポール対策」といって、橋の両脇に、高さのあるよく目立つ旗を一列に設置し、シマフクロウやワシがその上を通過するように誘導します。

橋の欄干に設置されたポール。シマフクロウやワシたちは、主食の魚を狙って川沿いを利用するため、川と道路の交差点となる橋での交通事故は多い
齊藤:
この間隔を狭めれば狭めるほど、道路業者はそれだけ数を設置しなければならなくなりますが、人間にとっても無理のないよう、猛禽類が認識できて、かつ人間にとっても極力負担のない間隔を、研究成果を基にして対象種に応じて選択しています。
オジロワシ・オオワシに関しては、車だけでなく列車事故も多いです。
車や列車にはねられて道路や線路の傍に横たわった野生動物の死体を求めてやってきたワシが、食べている最中に轢かれてしまうことも多いです。
事故対策として、轢かれた野生動物が回収されるまでの間、ワシが誘引されないように死体を覆い隠すことを目的としたシートの開発も環境省や民間企業と連携して進めています。

丸で囲っているのが覆隠シート。ワシがどの色に反応するのかを確かめるために行った実証実験にて

鉛中毒により神経症状と呼吸困難を起こしたオジロワシ
齊藤:
交通事故以外に、風力発電のプロペラとの接触事故や感電事故、鉛中毒などもあります。
──鉛中毒とは?
齊藤:
北海道ではだいぶ理解が進み、法の規制もあって銃弾の脱鉛化が進んでいますが、北海道以外では安価な鉛の銃弾がまだまだ普及しています。撃たれたエゾシカを食べたワシが、肉と一緒に鉛の銃弾の破片を飲み込んでしまうと、鉛が胃で溶けて中毒になるのです。
スチールや銅など、別の有毒ではない素材に変えてもらうべく、国への働きかけをしています。
発電用風車との接触事故(バードストライク)についてですが、風車のプロペラに当たれば、真二つになって死んでしまいます。
風のエネルギーを利用したいけれど、野生動物に迷惑をかけずにどうやって共生ができるのかを考え、ベンチャー企業と共同し、新型の「マグナス式風車」の開発を進めています。

現在も実験中のマグナス式風車。現段階はマグナス式風車に対する終生飼育個体の反応を記録している
齊藤:
感電事故については、送電鉄塔の危険な場所に猛禽類を接近させないための「バードチェッカー」と呼ばれる器具を開発し、北海道では2,500から3,000箇所で設置していただいています。
感電事故が起きた送電鉄塔の場所や環境を僕が一つひとつ検分して、同じような事故が再発しないよう、事故発生リスクがある地域の鉄塔に「ここからここまで、こういうふうにつけてください」と伝えて、電力会社の方で予め決められた停電計画のタイミングにあわせて、設置していただいているものです。

バードチェッカーの開発のために行った実験。バードチェッカーが設置された部分にはとまらない。終生飼育個体の協力の元、効果のある形を研究した
齊藤:
電力会社にとっても、停電は大きな支障になります。僕らとしては野鳥の感電事故を防ぐため、電力会社としては停電を防ぐため、見方はそれぞれ異なりますが、一緒に対策を取り組むことは可能だと思っています。
僕らのやることはただ一つ、「野生生物を護る」こと。
国土交通省だったり電力会社だったり、それぞれ協働する先は違うし、またそれぞれに異なる立場ですが、共通項を見つけ、それぞれの解釈のもと、ひとつの目標に向かってスクラムを組んでやっていくということ。
動物ファーストでも人間ファーストでもなく、人と野生生物が、より良いかたちで共に生きていくために、何ができるかを考え、働きかけていくことが、僕らの一番の役割だと思っています。

風車事故に遭ったオジロワシの放鳥シーン。背中に衛星送信機を装着している

交通事故で上嘴が欠損し、エサをつまみ上げることができない状態になってしまったオジロワシ”ベック”。歯科技工士とタッグを組み、レジンで義嘴を開発し、自力で採食できるようになった。義嘴の定期的なメンテナンスが必須であるため、野生復帰は出来ないが、獣医療やQOL向上のための技術発展に寄与してくれている
齊藤:
傷ついた個体の治療と野生復帰、また検分による原因究明については、環境省の事業というかたちでやっています。概ね何羽治療などの目安はありますが、収容個体は想定通りにはいきませんし、個体によって治療の程度も異なります。
我々が治療するのが何羽であろうと、何度手術をしようと、事業費としていただいているのは丸めていくらというかたちなので、治療すればするだけ、調査すればするだけ赤字状態ですが、とにかく救えるいのちを救いたい。治したいし、やれることはすべてやりたいと思っています。

事故により左脚の先を失ったオジロワシの幼鳥。巣立ち直後で収容されたため、野生で生きる術を知らず、また左脚が無いことから、野生に復帰できないと判断された。いずれは教育現場や活動普及の場で活躍してもらいたいため、馴化訓練(人に慣れさせる訓練)を行っている
齊藤:
内視鏡や電気メス、レントゲン、薬といった治療に必要なものは一切合切、独自に揃えています。最初から用意しておかないと、動物が来てからでは間に合いません。
ドクターカーで遠いところから運ばれてくる個体もいますが、北海道は広いので、ここから現場に向かい、帰ってきてからの治療だと間に合いません。帰りながら治療し、救命率を高めています。現在、30%台後半で救命ができており、これは世界の中でも高いレベルです。
──すごいですね。

麻酔下で手術をする齊藤さん
齊藤:
治療についてもそうですが、野生に返すまでのリハビリも、我々がどれだけ、どこまでやるかということがあります。また、ちゃんと野生でやっていけているのかを確かめて、はじめてその治療がよかったかどうかがわかります。
野生復帰の際には、衛星送信機というGPS装置をつけて放鳥しています。一台あたり数十万円するかなり高価なものですが、調査して「次に生かす」ということをやるためには必要不可欠なものです。
──治療した個体は、すべて野生に帰ることができるのですか。
齊藤:
いいえ。治療によって一命は取り留めたものの、片方の翼を失うなど重度の後遺症が残り、野生に帰ることのできない個体もいます。

終生飼育しているワシたちに給餌するスタッフ。オオワシ・オジロワシの主食となる魚を与えているところ
齊藤:
現在、猛禽類医学研究所には70羽近い終生飼育個体がいますが、その食費や、世話をするための人件費、環境を整えるための資金などは全て、自分たちの持ち出しです。
70羽近い個体の餌代を賄うと、お金はあっという間に飛んでいってしまいます。
終生飼育個体はここで暮らしながら、傷ついた仲間の輸血ドナーになってもらったり、交通事故や感電事故対策のために開発したものを試してもらったり、我々が開催しているバックヤードツアーで、参加した人たちに現状を伝える役割を果たしてくれています。
そこで得た収益を、不足している治療費や餌代、飼育管理費に充てています。
──終生飼育個体たちが、活動を支えているんですね。

土日・祝日の13時から開催しているバックヤードツアーの様子。猛禽類医学研究所の活動紹介や終生飼育個体の観察などを行っている

授業の一環として、シマフクロウ親善大使「ちび」と共に環境について学ぶ子どもたち
齊藤:
「獣医だから治せるんだ」とか「自分には何もできない」と思われる方がいるかもしれません。だけど、獣医が治せるのはごく一部です。
僕は獣医として、事故に遭ったり怪我をした猛禽類を治療しますが、それよりも、そうならない環境をつくることの方が、彼らにとってはよっぽど重要です。
僕らは、猛禽類を傷つける環境自体を治すために、僕らができるさまざまな「環境治療」に取り組んでいます。
テレビや新聞、学校の教科書などで活動を紹介していただいたり、SNSの発信、児童書、専門書を書いたりもしていますが、これらはすべて、環境治療のためのプロジェクトなんです。つまり、いろんな人に知ってもらうこと、伝えていくということも、非常に大切な環境治療なんです。
──徹底して治療し、研究し、各地に出向かれ、発信されていますが、齊藤先生はなぜ、そこまで彼らに寄り添うことができるのでしょうか。
齊藤:
治せたはずなのに、もう冷たくなって我々のところに運ばれてくる命があります。目の前で死んでいく命があります。目の前で苦しんでいる姿を見ると、「同じ人間の責任だから、なんとかしなきゃ」と思う。ただ、それだけのことです。
特別なことをしているわけではなくて、皆さん、きっと同じ立場になったら同じことをすると思う。

高病原性鳥インフルエンザに感染したオジロワシの研究治療。2025年7月までに、感染して生体収容されたオジロワシ14羽中10羽の投薬治療に成功(うち2羽放鳥)、加えてオオワシ1羽中1羽、タンチョウ1羽中1羽の治療にも成功している
齊藤:
愛護のためにやっているという感覚はありません。愛護ってどこか「治してあげるよ」というような、上から目線というか施しのような感じがするんです。そうではなく「共生」、「同じ目線に立つ」というのが重要であって、僕は、彼らには彼ららしく生きてもらいたい。
同じように人間も人間らしく生きていくにあたり、とはいえ石器時代に戻れるわけでもなく、電気を使いたい、環境を使わせてもらいたいということになった時に、野生生物にリスペクトを持って、「極力、彼らに迷惑をかけずに何とかできないか」という意識を持っていなければならないと思っています。

「傷ついたオオワシと向き合う約30年前の私。当時はほぼ一人で野生の命と向き合っていたが、今では一緒に活動するスタッフは10人に増えました。この30年あまりで希少猛禽類の保全に関する一般市民の知識や意識は格段に高まり、応援してくださる方々も大幅に増えたと実感しています」
齊藤:
僕らは毎日、人間として電気を使い、道路を使っていますよね。
電気はどこから来ているかと言ったら、原子力なのか風力なのか太陽光なのかわからないけど、環境にやさしいところからは来ていないわけでだし、道路を使い、車を使い、彼らの生活圏を奪っているのは事実です。これはどこかで遠くで起きている話ではなく、僕らがやっていること、僕らが作っていることなんです。そこから目を背けてはいけないと思います。
──齊藤先生の、野生生物、猛禽類に対する対等な眼差しが伝わってきました。彼らに対して、どのような思いを抱いておられるのでしょうか。
齊藤:
彼らは、誰も傷つかなくて済む社会、そのためのヒントを、私たちに教えてくれるメッセンジャーであり、スポークスマンです。
彼らが命がけで伝えてくれるメッセージを、僕らは「獣医学」という言語で紐解き、人間語に訳して、犠牲になった命が無駄にならないように、ただ提案するだけでなく実際に行動し、しかるべきところに、説得力のあるかたちで届けること。それが僕らの役割だと思っています。

目の前の命と向き合い決して諦めないこと、そして信頼できる方々とのコラボレーションが予想以上の成果をもたらしてくれることを教えてくれたオジロワシ”ベック”。歯科医師や歯科技工士とのコラボレーションにより完成した義嘴(ぎし)を上手に使って自ら食事をするベックの姿は見る者に感動を与えてくれる
齊藤:
世の中を動かすのは民意だけです。
そして民意が何を以て動くかというと、「根拠を持った情報」です。嘘偽りがあっちゃいけない。僕たちがここで得た情報を嘘なく発信して、少しずつ、草の根的に活動を進め、いつかはこんな活動が必要のない社会にならないといけないと思っています。
僕らのことを知ってくださった皆さまが、たとえば一人に話してくださったら、倍になりますよね。10人に話してくださったら、10倍になります。
目の前の小さなことから草の根的にやっていけば、きっと10年後、環境治療が進み、より良い共生社会ができているんじゃないかと期待しています。
──最後に、チャリティーの使途を教えてください。
齊藤:
チャリティーは、終生飼育個体の飼育費用(主に餌代)として活用させていただきます。
ぜひ応援いただけたら嬉しいです。
──貴重なお話をありがとうございました!

猛禽類医学研究所のスタッフの皆さん。環境省釧路湿原野生生物保護センター前にて

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜
齊藤先生の野生生物のいのちと対等に、真摯に向き合われる姿、揺るぎない信念に胸を打たれました。
資源をまるで自分のものであるかのように思い込み、さんざん環境を破壊して開発を進めてきた私たち人間。この行為の行き着く先は、一体どこなのでしょうか。
私たちが便利さを享受する一方で、傷つき、苦しみ、悲しむいのちがあるかもしれないということ、「共に生きる」ために私たちができることを、今一度考えてみませんか。
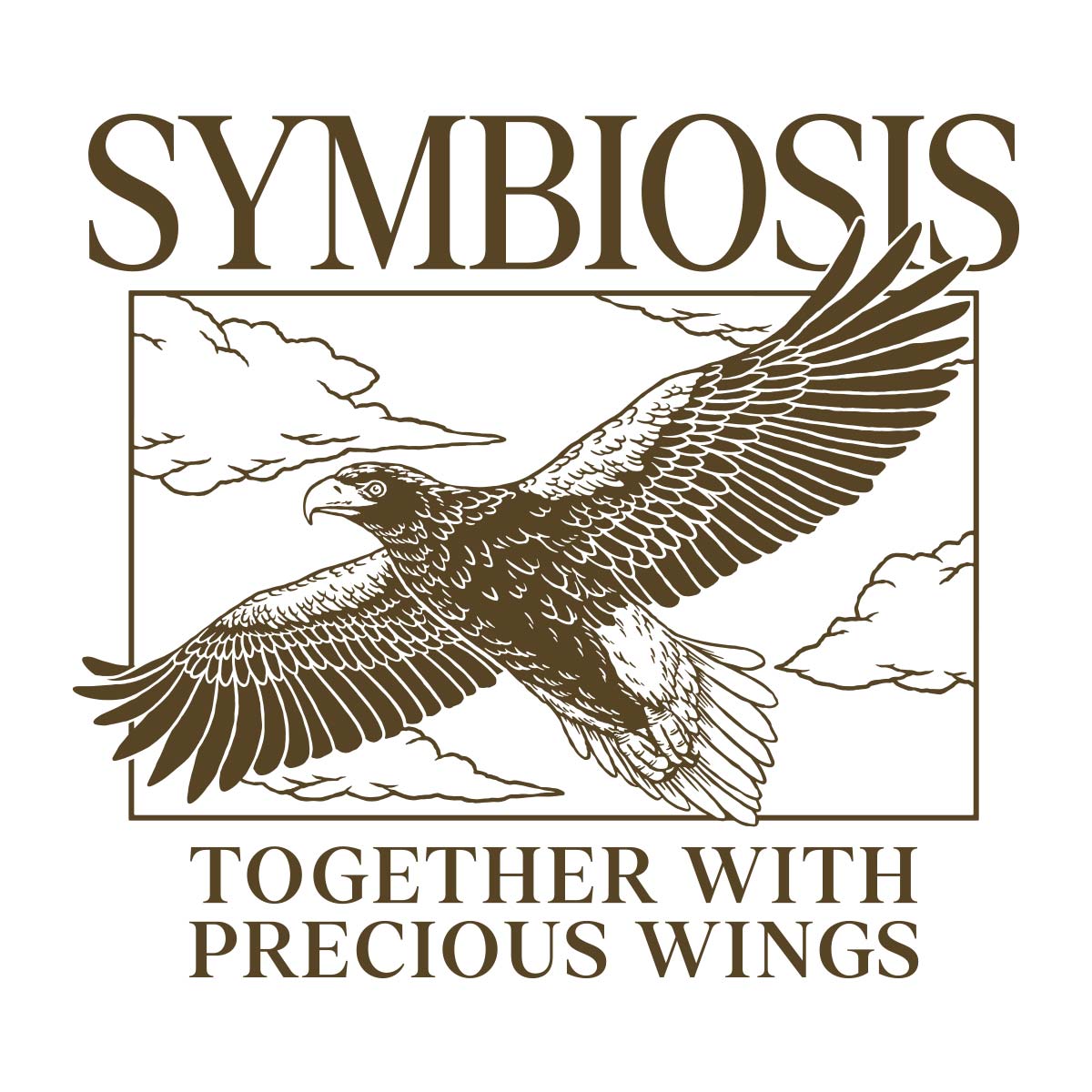

【2025/8/11-17の1週間限定販売】
翼を広げ、大空を高く飛ぶオオワシの姿を描きました。
勇猛に、気高く飛ぶ姿をリアルに描き、猛禽類をはじめとする野生生物が、ありのままの姿で、健やかに生きられる社会への思いを込めました。
“Symbiosis/ Together with precious wings(共生/ 尊い翼と共に)”というメッセージを添えています。
JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。
今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!