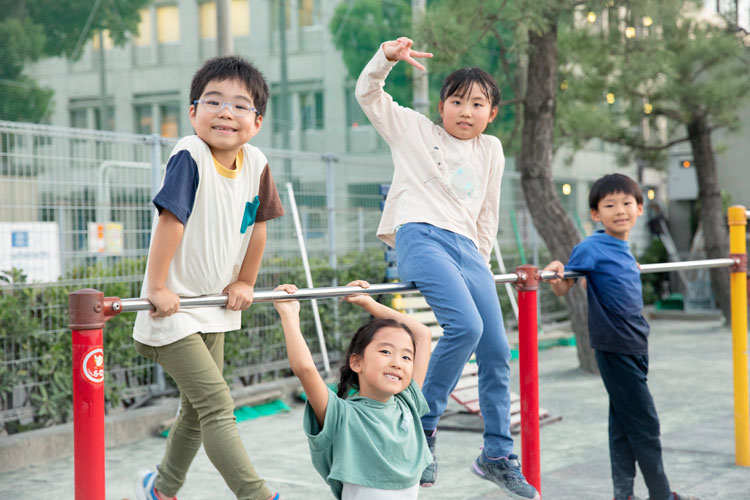
放課後や長期の休みに、日中仕事などで保護者が家にいない小学生の居場所として、子どもたちが遊んだり学んだりする「学童保育」。共働き世帯が約7割を占める今、年間151万人超(2024年、こども家庭庁)の小学生が利用登録しているといいます。
しかし、保育園と比べて数が圧倒的に少なく、待機児童(空きがなく、利用できない児童)が1万7,686人(2024年12月、こども家庭庁発表)おり、その数は年々、増加傾向にあるといいます。
「待機児童の問題は解決したのではと思っている方もおられるかもしれませんが、それは保育園の話であって、学童保育では全く解決していません。学童保育の待機児童数は3年連続で増加中です。子どもの成長にとって重要な放課後にはまだまだ課題が多く残っています」と話すのは、今週JAMMINがコラボする「放課後NPOアフタースクール」代表の平岩国泰(ひらいわ・くにやす)さん(51)。
20年前、娘が生まれたのをきっかけに、「放課後」の課題を知り、子どもたちの世界を豊かにしたいと活動を始めた平岩さん。
「子どもたちにとってどんな放課後が良いのかを、真剣にデザインしてあげられることが大切」と話す平岩さんに、活動について、放課後の可能性について、お話を聞きました!

お話をお伺いした平岩さん

NPO法人 放課後NPOアフタースクール
日本中の放課後を子どもたち一人ひとりにとってゴールデンタイムにすることを目指して活動しています。
INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO
RELEASE DATE:2025/03/17

アフタースクールの一コマ。友達と遊んだり、漫画を読んだり、思い思いに過ごします
──今日はよろしくお願いします。最初に、団体のご活動について教えてください。
平岩:
「小学生の放課後」のフィールドで活動しているNPO法人です。
具体的な活動として、地域社会で子どもを育てる、直営のアフタースクールを、東京、千葉、神奈川、埼玉の15拠点(2025年3月17日時点)で運営しているほか、このしくみを全国に広げるために、各地の自治体さんなどと共に、全国の放課後の居場所支援もさせていただいています。
さらに、さまざまな企業とタッグを組み、全国の放課後に体験活動を届ける取り組みや、放課後の重要性や課題をより多くの方に知っていただくための啓発・調査研究、政策提言も行っています。

水の大切さや科学の面白さを学ぶ企業協働プログラム
──どんな思いで、子どもたちの放課後に取り組まれているのでしょうか。
平岩:
ベースとして「放課後に、子どもたち一人ひとりが、思い思いに過ごすことができる」ということを大事にしています。
今の学校教育は「学習を通してこういうことを獲得してください」っていう、「今のあなた」ではなく「未来のあなた」から入るようなところがあると思っています。それは見方によれば「今のあなたでは足りないものがある」というふうにも捉えられて、目標に向かって努力することは大切ですが、それだけでは苦しい子どももいます。
ある調査で、将来に希望を抱いている子どもが日本では非常に少ないというデータもあります。生まれて5年や10年の子どもにとって、まだまだ目の前で起きていることが世界の全て。でも社会は広くて、目に見えるものがすべてではないし、いろんな生き方があるんだよということを伝えるのは、大人の責任でもあると思います。
子どもたちが「今の自分でいいんだ」と感じ、心から笑顔になれるように、放課後は、自分らしくあれて、自分の好きなことや、やりたいことができる場所であってほしいと思って活動しています。その先にきっと、子どもたちがワクワクするような未来もつながっているように思うのです。
時々、私たちはこの活動をミツバチのように思う時があって、あちこち飛び回って花から蜜を集めて巣に戻るように、いろんな資源を集めて、子どもに良いものを届けたい。私たちや各地のみなさんと共につくる放課後を媒介して、子どもと社会とにつながりが生まれるように思っています。
──そうなんですね。
平岩:
私たちのミッションは「日本中の放課後を、ゴールデンタイムに」。
小学生の放課後は、通算すると年間1,600時間(※低学年の場合)あると言われます。僕は、この1,600時間の中で、宝物のような物語とたくさん出会ってきました。

夢中になって遊ぶ放課後は、かけがえのない時間

それぞれのやりたいことを目掛けてかけだしていく様子
──1,600時間という放課後ですが、そのあり方も、一昔前と比べて様変わりしているのではないですか。
平岩:
この30年ほどで放課後から、「時間」「空間」「仲間」の「三つの間」が失われていっています。
この三つの喪失により、「放課後自体がなくなった」と言う人もいます。そこまでは言い過ぎだとしても、少なくとも子どもたちが自由に、好きなことをできる機会が非常に少なくなっています。
──なぜ失われてしまったのですか。
平岩:
三つの背景があると考えています。
一つは、共働き世帯の増加です。一昔前は、お母さんが専業主婦で家にいて、子どもたちは地域で遊ぶことができましたが、その在り方が変わったこと。
もう一つは、以前は子どもが当たり前に遊んでいた場所で、安全性を考慮して、さまざまな制約が設けられるようになったこと。また空き地がなくなるなど物理的に場所が減ったこともあります。
さらに、子どもたちが地域で過ごすことに対して、たとえば声がうるさいとかボール遊びはダメだとか、寛容さがなくなり、地域の見守る目も減ったこと。
このような背景から、大人が子どもたちの放課後の居場所や過ごし方を決めるという風潮が生まれていきました。
──確かに、私が生まれ育った地域でも、子どもたちが遊べる場所や遊んでいる姿が、明らかに減ったように思います。
平岩:
そのような中で学童保育に対するニーズが増加し、待機児童問題も深刻さを増しています。
学童保育の数が足りておらず、1万8,000人近くが待機児童になっており、今後も増えていく可能性があります。
保育園については、国が一気に数を増やしましたが、保育園をそれだけ増やせば、今度そこに預けられていた子どもたちが成長した時に、学童の方でも待機児童が出るということは、予測できたところもあります。国もこども家庭庁設立を皮切りに学童保育をはじめとする居場所づくりに積極的に取り組んでいますが、実態に追いつかない状態に今はあります。
──そういうことなんですね。
平岩:
学童保育は保護者の就労支援を目的にした「子どもを預ける場所」と認識されてしまっているように感じます。働く親を支えるために、子どもをなんとか預かってもらえれば満足という方々が多いように感じますが、「子どもにとってどんな放課後が良いのか」という視点も欠かせません。
──量だけでなく質も重要ということですね。
平岩:
その通りです。子どもたちにはそもそも放課後に自分の過ごし方を選ぶ権利がありますが、社会全体でその権利を保障しようという価値観へのアップデートが必要です。
放課後が、子どもたちの成長にとってどれだけ重要な場所であるかを社会全体が認識し、優先順位を変えていかないと、根本的な問題は解決しないと思っています。

「なにをしてもいい。なにもしなくてもいい」
──話していただいたような課題がある中で、団体として、放課後に大事にしていることを教えてください。
平岩:
子どもたち一人ひとりが自分の好きなことに自由にチャレンジできること、過ごし方を選択できるということを大事にしています。
学校では、子どもたちは過ごし方をほとんど自分で選ぶことができません。カリキュラムがしっかりとあるからです。でも学校はそこに意味があると言えます。
一方で、放課後は「自分で選ぶ」というところに価値があります。
自分で選ぶということをしないと、選択する力は身についていきません。最初はうまく選べないし、失敗もします。徐々にでいいのです。繰り返し選んでいくことで、選ぶ力が身についてゆくのです。
今日は元気に遊びたい、ゆっくりしたい、漫画を読みたい…。選択肢があって、一人ひとりが「自分で選ぶ」「自分で決める」ことが尊重される放課後を、真剣にデザインする必要があります。
──そうすると、どんな放課後になってくるのでしょう。
平岩:
私たちは、すでにある小学校施設という資源を活用し、地域社会と共に子どもを育てる「アフタースクールモデル」を提案しています。
移動も必要なく、子どもたちが好きに過ごせる空間がたくさんある学校施設を活用し、子どもの声を真ん中にした放課後を、日本の社会インフラにすることを目指しています。
──放課後もみんなで遊べていいですね。
平岩:
そうですね。また子どもたちに多様な体験機会がつくれるように、「市民先生」として、地域の方たちが協力してくださっています。
編み物、料理、スポーツ、音楽、海外の文化…、いろんなことを教えてくれる方が、地域にはたくさんいる。そのことも含めて、多様な選択肢があることが大事だと思っています。
──ワクワクしますね。子どもたちは楽しいでしょうね…!
平岩:
何をするにしても、「自分で選んだ」というベースがあると、皆、満足そうです。選んでやると、宿題ですら満足そうです。

放課後の理科室で科学実験!

生まれたばかりの娘さんと。娘の誕生が、活動のきっかけとなった
──話は少し変わりますが、平岩さんがこの活動を始められたきっかけを詳しく教えてください。
平岩:
娘が生まれた2004年、子どもが事件に巻き込まれる新聞記事を見て、その多くが下校時に起きていることを知って、初めて放課後に問題意識を持ちました。放課後にさまざまな課題があることを知り、娘が小学生になる6歳までに、父として良い放課後をプレゼントしたいと思ったのがきっかけです。
──娘さんの誕生をきっかけに生まれた放課後NPOアフタースクールは、これからどこへ向かっていくのでしょうか。
平岩:
これまでの放課後NPOアフタースクールは、まずは自分たちが居場所づくりや体験機会創出をしっかり行なっていくことに向き合ってきました。しかし今、私たちは自分たちの活動(場づくりの実践)と社会の変革を両輪で行う組織へと生まれ変わろうとしています。
これまで以上にさまざまなステークホルダーの皆さんと共に子どもたちの幸せに貢献する未来を放課後からつくっていきたいです。このようにご寄付という形で社会の応援を集め、全国の放課後に還元していくこともこれからの私たちの挑戦です。

「日本中の放課後をゴールデンタイムに」
──読者の皆さんに、メッセージをお願いします。
平岩:
子どもたち一人ひとりが、多種多様で素晴らしい興味関心を持っています。
日本中どこに生まれ育っても、子どもたちが自分のやりたいことを、思い切ってやれる放課後をみんなでつくりましょう。今回の企画を通じて放課後の課題や価値が広く伝わり、ゴールデンタイムな放課後につながっていくことを願っています。
──最後に、チャリティーの使途を教えてください。
平岩:
「放課後を、子どもたちにとってもっともっと楽しい場所に変えていきたい!」という思いを持った方たちが、全国におられます。
今回のチャリティーで、放課後の居場所の運営者や自治体の担当者の方たちに向けて、共に放課後づくりを学ぶイベントの開催費用として活用させていただく予定です。
ぜひ、アイテムで応援いただけたら嬉しいです!
──貴重なお話をありがとうございました!

「放課後NPOは現在15才。これからも皆様と共に」

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜
自分が子どもだった頃を振り返ってみると、放課後は「自分の時間」で、思いきり自分自身になれる空間でした。
誰にも支配されない自分たちだけの空間で、いろんな冒険や挑戦ができました。あまり意識したことがありませんでしたが、平岩さんのお話を伺いながら、放課後に本当にたくさんのことを学び、吸収していたんだなあと感じました。
時代が変わっても、そして子どもたちがどんな環境にあっても、「自分のやりたいことをやれる放課後」があることが、子どもたちの未来、日本の未来につながっていくのだと思います。


【2025/3/17~23の1週間限定販売】
さまざまなことに挑戦する人を、わくわくするタッチで描きました。
放課後の無限の可能性と、放課後を通して、子どもたちのさまざまな興味の扉と経験が広がっていく様子を表現しています。
“It is our time!”、「私たちの時間だ!」という言葉を添えました。
JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。
今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!