
日本の最西端・与那国島でかつて、人々と共に暮らしていた「ヨナグニウマ」を知っていますか。
50年ほど前まで、重い荷物を背中に乗せて、人々の生活を支えたヨナグニウマ。そこには馬と人とが共に生き、共に働き、支え合う風景がありました。しかし島にトラクターや自動車が普及したことで、馬は仕事と居場所を失いました。
「このままでは、ヨナグニウマが絶滅してしまう」。
42年前、50頭を切るまでに数を減らしたヨナグニウマを守りたいと、神奈川から与那国島に移り住んだ一人の若者が立ち上げた一般社団法人「ヨナグニウマ保護活用協会」が今週のチャリティー先。
ヨナグニウマと人とが、かつてのように触れ合える小さな馬広場。
ここでヨナグニウマと出会った若者たちが、やがて沖縄本島、久米島、石垣島…と各地に牧場を立ち上げ、ヨナグニウマの活躍の場を広げています。
ヨナグニウマ保護活用協会が、与那国島で最初に開いた「ヨナグニウマふれあい広場」。人手不足のために2018年に一度は閉鎖したこの広場を夫婦で引き継ぎ、2020年に「ちまんま広場」として再オープンした西山真梨子(にしやま・まりこ)さん(38)。2016年には陸上自衛隊の基地ができた与那国島ですが、「ヨナグニウマと人とが触れ合う場を守っていきたい」と話します。
ヨナグニウマについて、活動について、お話を聞きました。

お話をお伺いした西山さん

一般社団法人ヨナグニウマ保護活用協会
人とヨナグニウマとが共存できる社会を目指し、ヨナグニウマを有効に活用し、その保存に貢献することを目的に活動しています。
INTERVIEW & TEXT BY MEGUMI YAMAMOTO
RELEASE DATE:2024/05/13

「日本の端っこの浜・ナーマ浜での海馬遊び。子どもから大人まで、ご家族皆で楽しめます。馬に乗るだけでなく、馬を洗い触れ合い、透き通った海の中を尻尾につかまって引っ張ってもらう気持ちよさは格別です!」
──今日はよろしくお願いします。最初に、団体のご活動について教えてください。
西山:
ヨナグニウマ保護活用協会は、日本の最西端の島・沖縄の与那国島の在来馬である「ヨナグニウマ」の保存と活用を目的に活動しています。その昔、島の人たちの生活に欠かせなかったヨナグニウマを、再び人のパートナーとして活用することに力を入れています。
今から42年前の1982年、団体を立ち上げた、通称「まーくん」こと久野雅照さんが、「ヨナグニウマ 絶滅の危機」という小さな新聞記事を目にしたことをきっかけに、神奈川から与那国島に移り住んで活動を始めました。

スタッフ、常連のお客さん、助っ人さんたちの乗馬風景。「農道のクバの木の前で写真を撮るため静止。周りには美味しい草ばかりで道草の誘惑がありますが、馬たちは人の声に耳を傾けてくれます」
西山:
そこにたくさんの若者が集まるようになって少しずつ活動が広がり、現在、与那国島の他に沖縄本島、久米島、石垣島、静岡の伊豆の国、高知の四万十にも兄弟牧場があります。
私が夫と与那国島で運営している「ちまんま広場」は、1992年にまーくんが最初にオープンした「ヨナグニウマふれあい広場」の跡地を受け継いだ馬広場です。主に観光客と島民の方に向けて、ヨナグニウマと触れ合う機会を提供しています。

馬と過ごす西山家の日常。海牧場で、ボロとり(馬のうんちとり)のお手伝い。「広い放牧地のあちこちでうんちをするので、あっちこっちと回るのは大変ですが、子どもたちは遊びの延長でやってくれます」

小さく、模様が入っていない茶色なのが、ヨナグニウマの見た目の特徴。「アスファルトなどの道路の上を歩く時、硬い蹄(ひづめ)の音がポクポクと聞こえてきます。蹄鉄の音の代わりに響くこのかわいい音もヨナグニウマの魅力かも」
──ヨナグニウマについて、詳しく教えてください。
西山:
日本にいる在来馬8種類(北海道和種馬(道産子)、木曽馬(長野)、野間馬(愛媛)、対州馬(長崎)、御崎馬(宮崎)、トカラ馬(鹿児島)、宮古馬(宮古島)、与那国馬)のうちの一つです。その中でも下から2番目の小ささで、体高は120センチほど。サイズで分類するとポニーになります。英語表記すると「ヨナグニ・ポニー」なんですよ。
──そうなんですね。
西山:
色の濃さは個体差がありますが、模様などが入っておらず、ボディカラーが茶色一色のみなのが特徴です。蹄(ひづめ)が石のように硬く、蹄鉄を履いていなくても足を壊しにくく、島の人たちの暮らしの中で、仕事を手伝ってきた長い歴史があります。

東牧場(東崎)のヨナグニウマたち
──どのような仕事を手伝っていたのですか。
西山:
「馬が人の仕事を手伝う」というと、畑を耕したり鋤を引いたりするようなイメージがあるかもしれませんが、与那国島では畑は牛が耕していました。馬の仕事は、人が乗って移動することと荷物を載せて運ぶこと。小柄ながら力持ちで、サトウキビや米などさまざまなものを背中に載せて、島を歩いていたようです。
ところが戦後、車やトラクターが普及したことで、馬の仕事は減り、同時に、それまであった人と馬とのパートナーシップも失われていきました。まーくんが島に来た40年前、ヨナグニウマの数は50頭を切るまでになっていました。ちょうどその頃に島民による保存会ができ、保存のために島内の広い敷地にヨナグニウマを放牧するというかたちが、今日まで続いています。現在、島には130頭ほどのヨナグニウマがいます。
とはいえ、ただ数だけを増やしても、かつてのような馬の役割、人と馬との関わりがない中で、馬を大事に思う人がいなければ、長い目で見た時にヨナグニウマが生き延びていくことは難しいと思っています。ヨナグニウマを活用し、人と新たな関係を結びながら、馬を大事に思う人を増やしていきたい。それが私たちの一つの役割です。

子育て支援センターにて。「お馬さんの背中に乗せてもらったり、お鼻から出る温かい息を感じて、お子さんもお母さんもにっこり」

ちまんま牧場にて、農道を散策する「ミニトレッキング」を楽しみ馬広場に帰って来たところ。「馬の揺れに慣れたら、手綱を使って一人で歩かせることもできます」
西山:
「ちまんま広場」には、31歳と28歳の高齢馬を含めて8頭のヨナグニウマがいます。
普段は主に観光客の方に向けて、体験乗馬やトレッキング、海馬遊びなどの馬遊びを提供しています。一方で「島の方たちにこそヨナグニウマと気軽に触れ合ってほしい」というのが何よりの思いなので、月に一度の日曜日「ふれあい体験乗馬会」を開催しています。
この町民乗馬は「ふれあい広場」だった時代から、ずっと大事にしている行事です。毎回20人ほどの方に参加いただいていますが、先日は48人のご参加がありました。
──たくさん来られるんですね!
西山:
私たちの牧場では通常、30分の馬遊びで5,000円いただいていますが、ふれあい体験乗馬会は町民の方にヨナグニウマと気軽に触れ合っていただきたいという思いから、無料で開催しています。

「ふれあい乗馬会に、よく遊びに来てくれる島民の親子さんたち。子どもたちは保育園生の頃からヨナグニウマと遊んでます。乗馬会では素敵な家族写真も撮影できます。一緒に写るのはスタッフと、島に住む馬好きな助っ人さんたち。馬を曳くお手伝いに、いつも楽しみながら参加してくれて本当にありがたい存在です。皆いい笑顔!」
──そうなんですね。ちまんま広場で開催されるのですか?
西山:
時期により広場内で開催する時と、外で開催する時があります。
ビーチで開催する時は、馬に乗る順番を待つ間に、皆さんに浜辺の漂着ごみを拾ってもらうビーチクリーンをあわせて実施したり。集めたごみを馬に運ぶのを手伝ってもらうこともあります。
さらに島の小学校3年生以上を対象に、馬のお世話や乗馬で触れ合ってもらう「馬教室」や、島の小学校中〜高学年の放課後の課外活動「馬クラブ」、幼稚園や小学校低学年に向けての馬の授業、最近は子育て支援センターでも依頼され乗馬会を始めました。

馬の授業で、高齢の馬たちにごはんをあげ、ブラシがけをする4年生の児童たち
──子どもたちをはじめとして、島の方たちと馬との触れ合いを大事にしていらっしゃるのはなぜですか。
西山:
ヨナグニウマは昔からいる当たり前の存在で、特に馬を使って暮らしてきた方々にとっては、馬との生活にはかわいいだけではない、いろいろなご苦労や思いもあったと思います。
しかし数が少なくなっている現状を受け止め、貴重な在来馬がいなくならないように保存や活用が必要なこと、ヨナグニウマを後世にも残していくことに対して、島民の方たちにこそ積極的に関わってもらいたいからです。
「ふれあい広場」の時代に、まーくんが続けてきた子どもたちへの馬の活動に関わってきた中で、「ただ眺めるだけでなく、触れ合いやお世話、乗ることができる機会が子どもの頃から当たり前にあることが何より大切」だと感じ、「ちまんま広場」として独立した当初から、島の方たちとの時間はとても大切にしてきました。

ちまんま広場の馬たちが夏から秋にかけて暮らす放牧地「海牧場」にて。「人の声をよく聞く女の子チーム3頭(通称:女子校)は、放牧地に入るとそばに寄ってきます。虫や日差しをよけるために顔にマスクをつけている子は6歳のサクラ。ツンデレな性格です。マスクをつけていない2頭は奥からお母さんアマル(14歳)と娘ミーサ(5歳)のそっくり親子。夫の奥にいる2頭は、人を気にせずマイペースに過ごす高齢馬たち。まーくんが馬広場を始めた頃から、島の子どもたちやお客さんを楽しませてきた馬たちです」

野生に近い状態で生きる、北牧場のヨナグニウマの並んだお尻。「お腹の大きなメス馬たちの、揺れる尻尾が風吹く島を感じます」
──与那国島では、自然の中で馬が放牧されていますよね。そうすると、島の人たちは普段から馬と触れ合う機会があるのではないですか。
西山:
島内に馬の放牧地は3つあり、中には道路も含む所もあるため車で走っていて馬たちを眺めることは日常茶飯事です。
そのうちの2つの放牧地、北牧場と東牧場で暮らすヨナグニウマですが、80年代に保存会ができて、保存のために広い土地で放牧する今のかたちとなりました。
餌あげや世話などを一切しない野生のような状態で放牧されていますが、それぞれの馬には持ち主がおり、数カ月おきに頭数確認を行い、近親交配が進まないように雄の仔馬を出すなどの管理がされています。
──そうなんですね。

樽舞地区の馬広場。「ごはんをもらえた嬉しさで(?!)、ごろごろと転がるセン馬コウちゃんの後ろには、南牧場の雄大な崖。大自然の中で暮らす日常と、実は愛嬌たっぷりのヨナグニウマです」
西山:
人の干渉を受けず、のびのびと過ごす姿は一見しあわせそうですが、やはり厳しい自然の中を生きていくことにはなるので、長生きする馬はなかなかいません。
南の島とはいえ冬には強い北風が吹き、体感温度は12、3度ほどになりますし、食糧の草も十分とはいえず、またメスは常に子供を産み育てているので、よく見ると痩せている馬が多いです。皆アダンという植物の中に身を潜め、日除け、風除け、雨除けをしながら耐えています。
私たちの牧場にいる、人と一緒に暮らす馬たちは、こちらもアダンの生い茂る放牧地に放し飼いで、簡単な小屋があるくらいなので、日差しや雨風に耐える環境こそ似ていますが、お客さんを乗せて運動しているので筋肉がつき、草以外に飼料も与えていることから、体つきはいい体格をしています。
町の放牧地の馬が、おそらく10代くらいで亡くなっているのに対して、私たちの牧場にいる最高齢の馬の「キョンタ」くんは31歳です。

のんびり草をはむキョンタおじいちゃん。顔に白髪がある
──ご長寿ですね!
西山:
31歳のこの子は北牧場の出身で、小さい頃にまーくんの元にやってきた雄馬(今はセン馬)です。ちまんま広場にいるもう一頭の28歳の「ヨッシー」は「ふれあい広場」時代に北牧場出身の母馬(昨秋に永眠)より生まれ、5頭ほど出産を経て、穏やかな老後を過ごしています。先述したアマルのお母さんです。
どちらが正解ということではなく、同じ馬で二つの環境があるということも、ヨナグニウマのひとつの魅力であると思っています。

「ある日の夕方、北牧場に夕日を見に行った時のこと。断崖絶壁の端に一頭で佇むヨナグニウマに出会いました。近づいても逃げる様子がなく、群れから離れこんな場所で何を思っているのだろうと気になり、皆でしばらく見守っていました」

日本で一番最後に沈む夕日を、馬と一緒に
──西山さんは、どういうきっかけで与那国島に来られたのですか。
西山:
私は神奈川の相模原市出身で、山梨で働いていた2008年の職場の夏休みに、初めて与那国島を訪れました。5日ほどの滞在で島を何周もして、放牧の馬に驚きましたし、まーくんの「ふれあい広場」で馬遊びも楽しみ、馬の世話にも通って、すっかりヨナグニウマが大好きになりました。
山梨に戻った後もヨナグニウマのことが忘れられず、お金を貯めてから仕事を辞め、2011年4月に再び、「ふれあい広場」の住み込みボランティアとして、馬のことを学ぶため島を訪れました。半年ほどで地元に帰ると周りには話していましたが、馬に触れれば触れるほど「もっと関わりたい」という気持ちが大きくなりました。

海牧場にて、夕方の馬のお世話。「日によりますが、学童から帰ってきた長女も参加して、家族皆で行います。ブラシをかけたり目やにをとったり。自然放牧しているので、馬の目に汚れや砂などが入って涙を流すこともあるんです」
西山:
そしてまた「いつか自分の馬と一緒に暮らしたい」という夢を抱くようになりました。そのまま「ふれあい広場」のスタッフになり、同じく広場で働いていた夫と結婚し、今に至ります。
──「自分の馬と暮らす」という夢をかなえられたんですね。
西山:
そうですね。最初は馬のブラッシングさえ怖いぐらいだったんですが、「自分の馬と暮らしたい」という夢ができてからは、もっとできるようになりたいと一生懸命でした。
私は不器用で、これといった特技もありません。落馬は他のスタッフの誰よりも多かったし、大きな怪我もしました。それでも馬と関わることを辞めたいと思ったことは一度もなかったし、馬のために何ができるか、いかに素早くたくさんのおいしい草を刈ってあげられるかとか、そんなことばかり考えて実践していました。

ナーマ浜にて、ひとりで海につかるアマル。「スタッフが先に浜に上がっても、いつまでも動こうとしません。仔馬の頃、お母さん馬のヨッシーが海馬遊びをする横で泳いだり、人に体を洗われて育ったので、暑い夏に入る、冷たく気持ちいい海が当たり前。馬たちにとっても、人と共に暮らすことで知る喜びがある気がします」
西山:
一頭の馬が感じていることをくみ取ったり、子どもたちやお客さんに馬遊びを通して楽しんでもらえる自信はつきましたが、もっともっと知識や技術を吸収して、まだまだ上手になりたいと思っています。今、守るべき馬たちがいて「ここから離れられないな」と感じています。
──奥深いんですね。
西山:
まーくんがこの島に来て40年、牧場ができて30年以上になりますが、島にも少しずつ、種が蒔かれていると感じます。
私が「ふれあい広場」でスタッフとして働いていた頃、町民乗馬に毎回参加し、広場に毎回通っていた女の子がいます。与那国島には高校がないため、進学する子どもたちは中学卒業と同時に島を離れるのですが、彼女は中学を卒業して島を出た後も沖縄本島にある兄弟牧場「うみかぜホースファーム」にお手伝いに通ってくれたり、ヨナグニウマが好きな気持ちは変わらずにいてくれて。

「『体は小さくても、お世話をしてあげたい心は誰よりもあるんだ』。小さな子のそんな気持ちに向き合ってくれるようなやさしい雰囲気が、馬にはあるように思います」
西山:
25歳になった今、「リモートで仕事ができるから」と島に帰ってきて、時折、ちまんま広場に助っ人として来てくれています。彼女が小さい時にヨナグニウマに乗せてもらったように、今の子どもたちを馬に乗せたり楽しませてあげたりする姿を見ていると、この活動が、確かに島の中でつながってきていると感じます。
──素敵ですね。
西山:
ヨナグニウマは、可能性のある馬です。子どもたちが大きくなって、たとえ島を離れることになっても、故郷で馬と触れ合った記憶は、きっと何か次につながると信じています。

「町民の乗馬会で島の子を乗せて歩く彼女は、子どもの頃から町民乗馬に毎回参加してくれていました。子どもの頃から変わらぬ笑顔のそばに、いつもヨナグニウマがいました」

島の南・インビ岳にそびえ立つ監視レーダー
──与那国島のすぐお隣は台湾ですが、最近、台湾有事(中国による台湾への軍事侵攻)が取り沙汰されていますね。そのあたりで、感じていらっしゃることはありますか。
西山:
関東にいる両親たちも「何かあった時はどうするの」と心配していますが、家族と馬と、ここで根を張って暮らしています。もちろん常に情報は追いつつ、それでも今の時代、どこに住んでいても何が起きるかわからないのは同じです。だったら好きな場所で、好きな仕事をしていたい。大好きな与那国島で、大切な家族と、馬を守っていきたいと思っています。

年に数回、はっきり見えることもあるという台湾の山並み。「与那国から台湾までの距離は約111キロ。こんなに近いのに、常に見えないのは不思議です」
西山:
私が与那国島に移住した2009年、基地建設の話が持ち上がり、2016年に陸上自衛隊与那国駐屯地が完成しました。基地建設の賛成派と反対派で対立があり、島の中によくない雰囲気があったように感じます。
島の中に基地や監視レーダーができ、島の環境は変わってきていることは事実です。そのことを懸念して、島を出た方もいます。ただ、私はヨナグニウマと与那国島が好きで、外から移住してきました。意見は分かれると思いますが、個人的な思いとしては、賛成であろうと反対であろうと、どんな方にもヨナグニウマに会いに来てほしいと思っています。
──皆のヨナグニウマなんですね。

「昨年の1月、ふれあい広場時代からの長い付き合いの北海道からのお客さんと、『ヨナグニウマのお世話をしてみたい』と、同じく北海道からボランティアとして数週間滞在していた青年。なんとこのお二人、小学校1、2年生の時の担任の先生と教え子という間柄でした!『今、お手伝いに来てくれてる〇〇くんです』と紹介した途端、さすが先生!教え子の顔と名前を覚えていて、すぐにピンときたようです。まさに奇跡を目の当たりにした瞬間でした。先生は与那国島や広場の馬の話を、教室の教え子たちに話して聞かせたこともあったそうです。与那国島やヨナグニウマが引き合わせた、嬉しい再会でした」

世の中が変化しても、変わらないヨナグニウマの佇まい。「乗馬会の合間に、ふと優しいまなざしを人々に向けるミーサちゃん。ミーサとは、与那国島の島言葉で『新しい』という意味です」
──読者の方に、メッセージをお願いします。
西山:
実際にその場所を訪れたり触れたりしなくても、バーチャルでいろんな体験ができる時代です。でもやはり、リアルでしか得られない、リアルだからこそ得られる感覚や癒しがあると思っています。
ぜひヨナグニウマに会いに、一度島に足を踏み入れてもらえたら嬉しいです。もしかしたら、人生観が変わるかもしれません。
──最後に、チャリティーの使途を教えてください。
西山:
チャリティーは、長年続けている町民のふれあい体験乗馬会のための資金として活用させていただく予定です。ここ与那国島だけでなく、石垣島、久米島の兄弟牧場でもほぼ無料、沖縄本島では格安でヨナグニウマとふれあう機会を提供しています。
触れ、その良さを知ってもらうことで、ヨナグニウマを次世代に残していきたい。
ぜひ、アイテムで応援いただけたら嬉しいです。
──貴重なお話をありがとうございました!

「4月、クルーズ船で来られた外国の方々に、ヨナグニウマたちと触れ合っていただくお仕事をした時です。与那国ならではのクバ笠をかぶってお出迎えしました」

インタビューを終えて〜山本の編集後記〜
西山さんから送っていただいた、与那国島のヨナグニウマたちのお写真!どれも息を飲むような美しさで、一瞬で引き込まれました。自然の中で、人との暮らしの中で、豊かに生きる様子が写真から伝わってきます。今すぐは無理ですが、いつか機会があったら与那国島を訪れてみたいと思いました。
人との暮らしの中で、大切な役割を担ってくれていたお馬さんたち。人々に愛され、その暮らしの中で、後世へと豊かに残っていくことを願います。
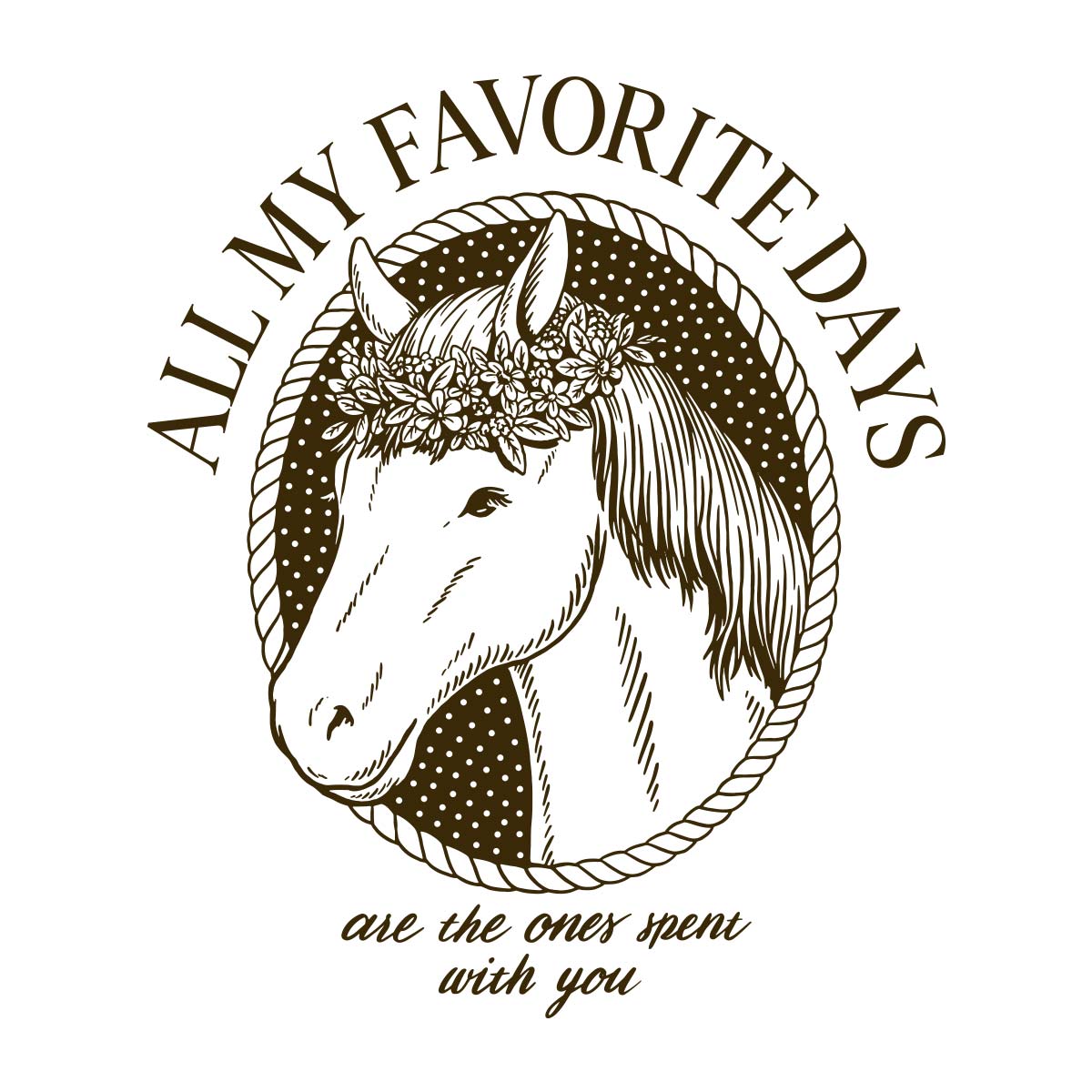

【2024/5/13~19の1週間限定販売】
頭に花かんむりをのせ、やさしい表情を浮かべるヨナグニウマを描きました。馬と人とが過ごす、穏やかで素敵な時間。ヨナグニウマとともに生きてきた歴史、ヨナグニウマへの慈しみや感謝を表現しています。
“All my favorite days are the one spent with you(あなたと過ごした日々が、私の一番好きな日)“というメッセージを添えました。
JAMMINは毎週週替わりで様々な団体とコラボしたオリジナルデザインアイテムを販売、1点売り上げるごとに700円をその団体へとチャリティーしています。
今週コラボ中のアイテムはこちらから、過去のコラボ団体一覧はこちらからご覧いただけます!